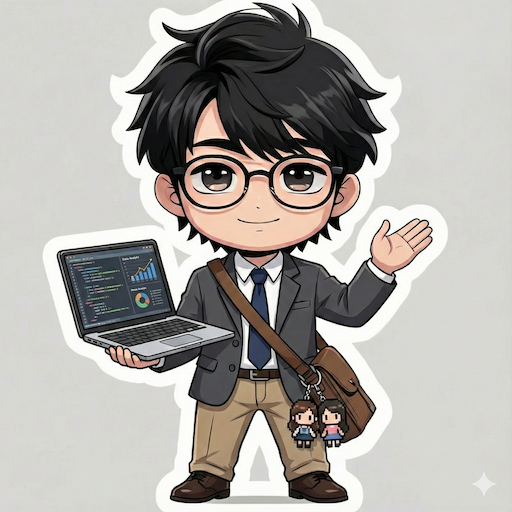FP3級の資格取得に向けて、勉強中です。
-
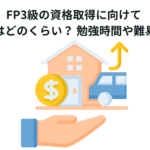
-
FP3級の資格取得に向けて 合格率はどのくらい? 勉強時間や難易度は?
FP3級の資格取得に向けて、勉強を始めました。 合格率は8割くらいと、比較的に難しくない資格なようです。 勉強に使っているのは、下記の本です。 自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。 こんな方 ...
続きを見る
勉強に使っているのは下記の本です。
自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。
こんな方におすすめ
- FP3級の資格取得を目指している方
- 資金計算について知りたい方
- 人生3大資金について知りたい方
資金計算について
最近、流行りの「複利の効果」。
よくわからなかったけれど、勉強してわかるようになりました。
6つの係数とは
資金計画においては、6つの係数が存在します。
- 終価係数
- 原価係数
- 年金終価係数
- 減債基金係数
- 資本回収係数
- 年金現価係数
1と2がまとまった資産の運用に関する係数、3と4が積み立てで資産運用する係数、5と6が逆に資産の取り崩しの係数です。
終価係数
100万円を年利3%で複利運用すると10年後どうなる?
10万円 ✖︎ 1.344 = 134万4,000円
上記赤下線が終価係数です。1.03の十乗ですね。
以降も赤下線でそれぞれの係数を表します。
現価係数
10年後に100万円にしたいなら3%で複利運用すると今いくら必要?
100万円 ✖︎ 0.7441 = 74万4,100円
年金終価係数
毎年10万円を10年積み立てる(総額投資は100万円)を年利3%で複利運用すると10年後どうなる?
10万円 ✖︎ 11.464 = 114万6,400円
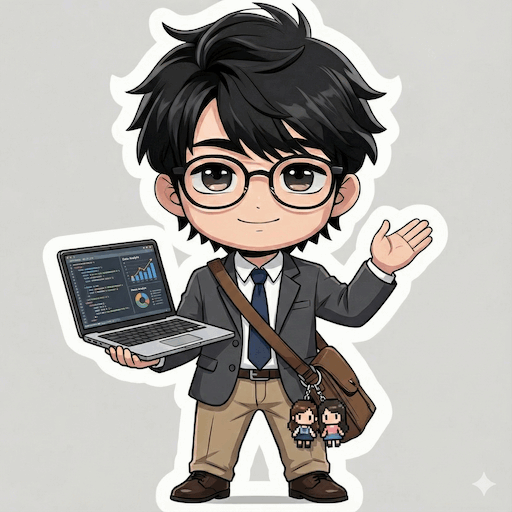
同じ100万円の投資でも一括投資のほうが20万円くらいお得なんですね
もちろん、これは安定的に3%の複利で運用できた場合です。
減債基金係数
100万円にしたい場合、毎年いくら積み立てれば良い? 年利は同じく3%。
100万円 ✖︎ 0.08723 = 8万7,230円
資本回収係数係数
100万円を年利3%で運用しながら10年で取りくずすと、毎年いくら使える?
100万円 ✖︎ 0.11723 = 11万7,230円
1万7,230円分が複利の効果ということですね。
年金現価係数
毎年10万円ずつ10年間使いたい。元の資産はいくら? 年利は同じく3%。
10万円 ✖︎ 8.530 = 85万3,000円
人生の3大資金とは
人生の3大資金は下記の3つです。
- 教育資金計画
- 住宅資金計画
- 老後資金
教育資金計画
子ども1人につき、大学卒業まで1000万円〜2000万円かかると言われています。
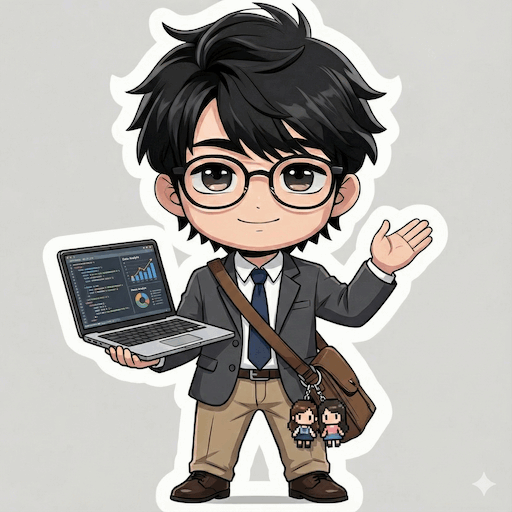
うちは子どもが2人います、、、
資金を準備する方法は3つです。
子ども保険(学資保険)。
国の教育ローン。子ども1人につき原則350万円までで18年返済期間がある。ただし、世帯の所得制限がある。
奨学金。第一種と第二種がある。
住宅資金計画
一般的には住宅ローンを組みますね。
金利の種類としては、固定金利型、変動金利型、固定金利期間選択型の3種類があります。
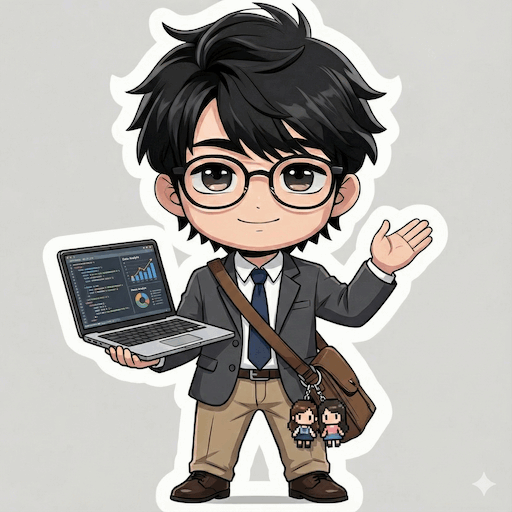
うちは変動金利です。これからの金利上昇が心配です。
ローンの返し方は2種類あります。
元利金等返済と元金均等返済です。
元利金等返済は返済額が一定、元金均等返済は元金額に応じて返済するので最初の返済額が大きく徐々に減っていきます。
利息は元金にかかるので、元金等返済のほうが最初にたくさん返済するので、総返済額は減ります。
上の資金計画であるように複利の効果は大きいので、元利金等返済で余るお金を運用に回すのも手な気もします。
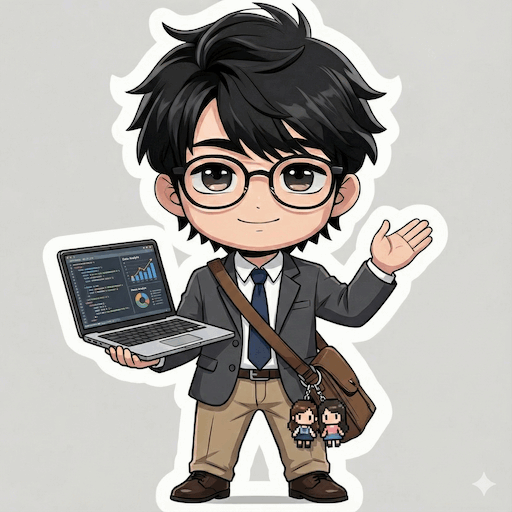
どっちの方法がいいんでしょうね。若い時に使えるお金が多い方がいい気も
ローンの繰上げ返済も期間短縮型と返済額軽減型があります。
期間短縮型は毎月の返済額は変わりませんが、期間が短くなる繰上げ返済で、返済額軽減型は毎月の返済額が減るような返し方です。
いまは利息がまだ小さいので、繰上げ返済をするメリットはあまりないと言われていますね。
さらにローンには団体信用生命保険(団信)が付くので、保険も含まれていることも焦って返す意味はないと言われる要素の一つです。
老後資金
リタイアメントプランニングといいます。
退職金、年金、貯蓄を使って生きていくことになります。
老後2人に必要な最低限の生活費用は約23万で、ゆとりある老後生活だと約38万円だそうです。

お金たくさんいりますね
資金計算と人生3大資金についてのまとめ
FP3級の資格を取得すべく、勉強内容について整理をしました。
6つの係数を学んだことで、複利の効果を改めて実感しました。
新NISA頑張りたいと思います。
あと、やはり子育てにお金はかかりますね。