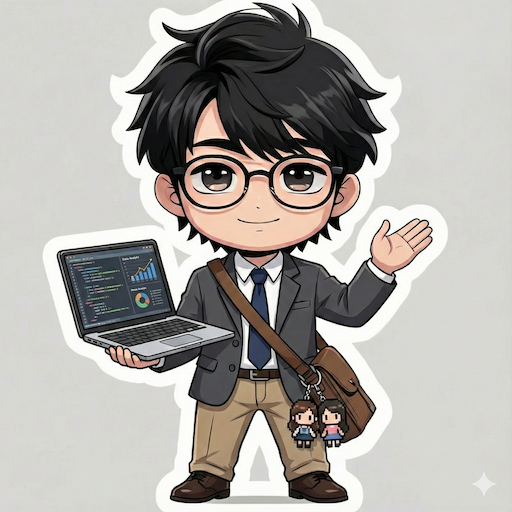FP3級の資格取得に向けて、勉強中です。
-
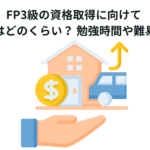
-
FP3級の資格取得に向けて 合格率はどのくらい? 勉強時間や難易度は?
FP3級の資格取得に向けて、勉強を始めました。 合格率は8割くらいと、比較的に難しくない資格なようです。 勉強に使っているのは、下記の本です。 自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。 こんな方 ...
続きを見る
勉強に使っているのは下記の本です。
自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。
こんな方におすすめ
- FP3級の資格取得を目指している方
- 社会保険について知りたい方
社会保険について
社会保険は下記を基本とします。
- 医療保険
- 介護保険
- 年金保険
広い意味で、労災保険や雇用保険の労働保険を含みます。
医療保険とは
日本国民全員が公的医療保険に加入する国民皆保険制度を採用しています。
- 健康保険:会社員とその家族が加入
- 船員保険:船員として船舶所有者に使用される人
- 共済組合:国家公務員、地方公務員、私学の教職員
- 国民健康保険:上記以外の方が対象
上記とは別に75歳以上になると「後期高齢者医療制度」があります。
健康保険とは
被保険者と被扶養者の病気やケガ、出産、死亡について保険が給付されます。
主に「中小企業の会社員を対象とした全国健康保険協会の協会けんぽ」と「大企業の会社員を対象として健康保険組合の組合健保」があります。
健康保険の保険料
保険料は協会けんぽは都道府県ごとに異なり、組合健保は組合ごとに異なります。
保険料は原則会社と被保険者が半分ずつ労使折半となります。
健康保険の給付内容
給付内容は、6つです。
- 療養の給付
- 高額医療費
- 傷病手当金
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 埋葬料
療養の給付や高額医療費は、医療費の負担をまかなってくれる保険です。
傷病手当金は、働けなくなった時に支給されるお金のことです。
出産育児一時金や出産手当金は、出産に伴い支給されるお金のことです。
最後の埋葬料は死亡時に支給されるお金です。
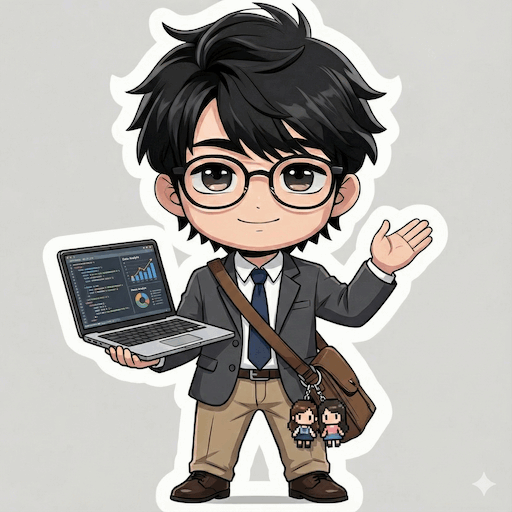
人生のいろいろな場で支給されるお金がありますね
国民健康保険とは
国民健康保険の保険料は市区町村によって異なります。
給付内容としての違いは、休業中の補償となるような傷病手当金と出産手当金がでないことです。

自営業の人は病気や出産で仕事がなくなったら、そのまま収入に響いてしまいますね
後期高齢者医療制度とは
75歳以上を対象とした制度です。
保険料は原則年金からの天引きとなり、市区町村が徴収を行います。
介護保険
介護の必要性があると認定された人の保険です。
65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上を第2号被保険者といいます。
下記の年金の被保険者では、自営業や学生を第1号被保険者、会社員や公務員を第2号被保険者というので、混同しないよう注意が必要です。
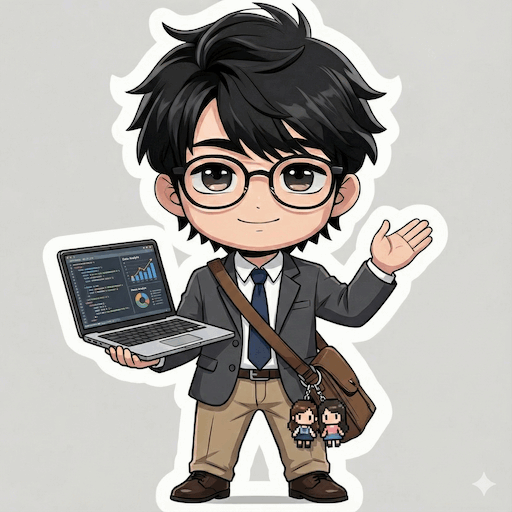
なんで同じ言葉使うんだろう、、、
年金保険
年金保険には、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2つがあります。
国民年金は全ての人が加入を義務付けられており、会社員や公務員は合わせて厚生年金にも加入しています。
- 自営業や学生は第1号被保険者
- 会社員や公務員等は第2号被保険者
- 第2号被保険者に不要されている配偶者は第3号被保険者
上記3つに分けられます。
リケイパパの場合は、大学院に行きましたので、大学院卒業までの間は第1号被保険者で、会社員になってからは第2号被保険者というわけですね。
国民年金保険料の免除制度と猶予制度
国民年金の保険料は免除と納付の猶予してもらえる猶予制度があります。
有名なの産前産後期間の免除と学生納付特例制度です。

学生納付特例制度は単なる猶予制度って知らなかったです
学生の間は学生納付特例制度で国民保険料の納税を免除されますが、10年以内に追納しないと、将来もらえる年金が減ります。
年金の給付
老齢給付と障害給付と遺族給付の3つがあります。
老齢給付
「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」があります。
老齢基礎年金の概要は下記です。
- 全員が対象の年金(国民年金)
- 20歳〜60歳まで保険料を納めると、65歳から受け取れる
- 自営業・会社員・無職など、すべての人が共通で加入
- 金額は一律(満額で年額 約78万円/2025年度時点)
老齢厚生年金の概要は下記です。
- 会社員・公務員などが対象(厚生年金)
- 基礎年金に“上乗せ”される年金
- 65歳からもらえる(一定の条件で60歳代からも可)
- 金額は給料の額と加入期間によって変わる
障害給付
病気やケガをしたことで障害者になった場合の給付です。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
遺族給付
公的年金の被保険者や被保険者であった人が死亡した時に、残された遺族の生活保障を目的に支給される給付のことです。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金の受給要件は下記です。
- 国民年金の被保険者である間に死亡した人
(=20歳以上60歳未満で加入中だった人) - 国民年金の被保険者だった人で、60歳以上65歳未満かつ日本国内に住んでいた人
(=60歳以降も任意加入中だった人が対象) - 老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年以上)を満たしていた人
ただし、原則として、保険料の納付状況が「原則として全期間の3分の2以上」という条件を満たす必要があります。
遺族厚生年金の受給条件は下記です。
受給できる遺族には順位があります。上の順位の人がいれば、下の順位の人は受け取れません。
| 順位 | 対象となる遺族 | 受給要件 |
|---|---|---|
| ① | 配偶者(妻 or 条件付きで夫)、子 | ・子は18歳到達年度の末まで(障害児なら20歳未満) ・夫は55歳以上で60歳から受給可(子がいれば55歳から) |
| ② | 父母 | 55歳以上(60歳から支給) |
| ③ | 孫 | 条件は子と同様 |
| ④ | 祖父母 | 55歳以上(60歳から支給) |
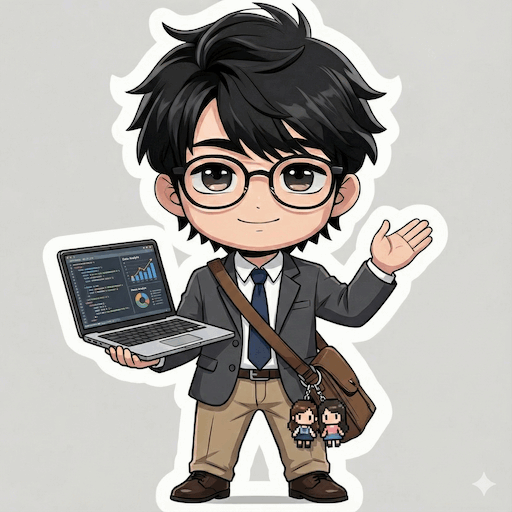
夫の場合は年齢制限があって、専業主夫の人には厳しいですね
夫の場合は、中高齢寡婦加算の適用もないです。
労災保険
仕事や通勤中に事故などでケガや病気になったときに給付が行われる保険のことです。
事業者負担になります。
療養で賃金がもらえない時に、休業補償給付が受けられて、給付基礎日額の6割がもらえます。
ただし、実際には休業特別支給金の上乗せがあるため、最終的に8割相当が支給されるのが実情です。
ポイント
労災保険の対象は仕事中のケガや病気で、傷病手当金(健康保険)は私的な病気・ケガという違いがあります
雇用保険
失業時や、教育訓練を受けたときなどに、失業等給付を支給する保険です。
事業主と被保険者の両方が負担します。
メインは2つです。「失業等給付」と「育児休場給付」です。
失業等給付
雇用保険の給付のうち、働くことに関する支援(就職・再就職・転職など)を目的とした給付の総称です。
求職者給付
失業している人が、就職活動中に生活を支えるための給付。
代表的な給付:基本手当(いわゆる失業手当)
他にも、技能習得中に支払われる手当(受講手当・通所手当)なども含まれる。
条件:就職の意思・能力があること、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
就職促進給付
早く再就職できた人や、就職が困難な人を支援するための給付。
代表例:
再就職手当(早期に就職した場合に支給)
就業促進定着手当(再就職後の賃金が下がった場合の補填)
移転費・広域求職活動費など(転居・遠距離面接の費用補助)
教育訓練給付
在職中または離職後に、スキルアップや資格取得などの教育訓練を受けた場合に支給される。
一般教育訓練給付金:支払った費用の20%(上限10万円)
特定一般教育訓練給付金:40%(一部講座に限り上限20ま年)
専門実践教育訓練給付金:最大70%(看護学校やIT資格講座など)
雇用継続給付
高年齢者や育児・介護をしながら働く人が、働き続けられるよう支援する給付。
代表例:
高年齢雇用継続給付(60歳以降も働く人への補助)
介護休業給付(家族の介護のための休業中)
育児休場給付
以前は、雇用継続給付の中に含まれていましたが、2020年(令和2年)4月の雇用保険法改正による制度変更によって外にでました。
この変更の背景には、育児休業給付の支給総額が増加し、一般の求職者給付を上回る見込みがあることや、景気変動の影響を受けにくい育児休業給付を、景気に左右されやすい失業等給付と切り離すことで、財政運営の透明化を図る目的があります。
育児休業開始前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あると、子どもが1歳(最長2歳)になるまで、休業前賃金の67%相当額が半年間支払われます。
半年以降は50%です。
2人までは連続でもらうことが可能です。
社会保険についてのまとめ
FP3級の資格を取得すべく、勉強内容について整理をしました。
社会保険も整理すると、いろいろわかるようになりました。